今回は文系大学院の研究計画書の書き方を具体的に説明していきます。

私自身、文系大学院の入試対策をこれまで請け負った経験があります。研究計画書についての指導は400名にものぼり、合格率も95%は確実に超えています(東大や京大などの最難関校も同様の実績数です。)。超有料級なものを今回説明していきますのでぜひ何度でも見られるようにしておいてください。
ちなみに、テーマなどの考え方については以下に紹介させていただいておりますのでご参照ください。


文系大学院の研究計画書の構成
文系大学院の場合にはおおよそ字数は2000字~3000字での構成を求められることが多いです。今回は一般的な2000字での説明をしていきます。
私が推奨する研究計画書の構成は以下の通りです。
・研究の目的(200字程度)
・研究の背景(400字程度)
・先行研究の検討(700字程度)
・研究の方法(400字程度)
・研究のスケジュール(300字程度)
具体的な内容について簡単に説明をしていきます。
はじめに研究の目的を端的に述べましょう。
「本研究の目的は○○を明らかにすることである」
「本研究は○○を明らかにすることを目的とする。」
研究の背景では大きく2つの内容を記載しましょう。
1つ目はなぜこの研究をしたいと思ったのかの「個人的な動機」です。ここでは、具体的に「こんな経験をしたから」というエピソードを記載してください。ここで重要なのは具体的なエピソードを記載することです。特に大学院入試では「思い」が重要になるので、個人的な動機にいかに熱意を乗せるかがポイントになります。
2つ目はいかにその研究が社会に役立つかという「社会的な意義」です。研究は常に「社会的な意義」が求められます。もし個人的な動機でしかなければそれは「ただの趣味」です。わざわざ大学院で研究するものでは無いと判断されます。社会的な背景を踏まえてご自身の研究がどのような意義があるのかを述べていきましょう。
研究テーマを考える際に、最初の「思いつき」レベルでは正直それはほとんどの場合で他の研究で解決されていると思ってください。世の中にはその専門家がたくさんいます。専門家たちはそれで生計を立てています。「思いつき」程度では、専門家たちに敵うはずがなく、ほぼやりつくされているものです。
だからこそ、先行研究をしっかりと踏まえたということがとても重要になります。書き方は、「○○は明らかになっている。しかし、○○については明らかになっていない。だからこそ、本研究では○○を扱っていきたい」という流れにすることが重要です。
実はここが一番の重要なポイントになります。研究で「明らかにしたいこと」に対して、「どのように具体的に明らかにするのか」を記載するのがこの部分になります。「質的調査」や「量的調査」という漠然としてものではなく、具体的に○○を明らかにするために、○○を行う、という文脈で記載しましょう。また、1つ1つ妥当性が必要です。例えば、顧客満足度を図るためのアンケートを行うとして、あなたの作成したアンケートが本当に顧客満足度を図るための内容として妥当なのかどうか、をしっかりと考える必要があります。そう考えると、本当に難しいということがお気づきいただけると思いますが、一番の対応策としては「先行研究の方法」を真似ることです。つまり、○○の研究で行われた調査方法を使用するとすることでこの「妥当性」をクリアしていくイメージです。
大学院入学後の2年間をおおよそ4タームにわけて、各タームで何を行うかをスケジュールとして記載してください。
以上の内容にて構成いただければ間違いなく構成面では合格できます。
内容については具体的な例もお示しできますのでいつでもお問い合わせいただければと思います。



今後も大学院入試の勝ち方を共有していきますのでぜひブックマークをお願いします!
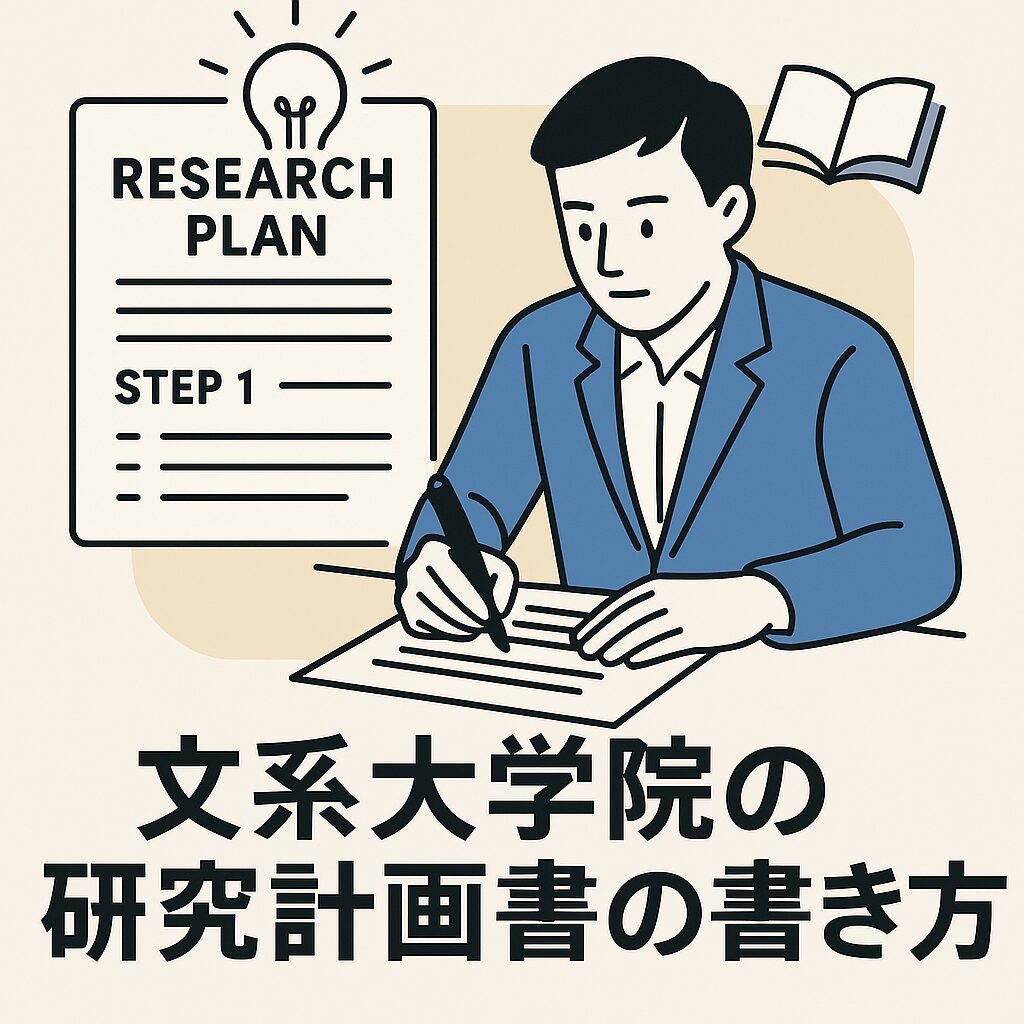
コメント