大学院入試の合否を分ける“最大のポイント”は何か?

私自身、文系大学院の入試対策をこれまで請け負った経験があります。研究計画書についての指導は400名にものぼり、合格率も95%は確実に超えています(東大や京大などの最難関校も同様の実績数です。)。超有料級なものを今回説明していきますのでぜひ何度でも見られるようにしておいてください。
結論から言うと、
それは「この人は卒業できるか?」という面接官の見極めポイントを押さえているかどうかです。
筆記試験や研究計画書、面接はすべて、この一点を見抜くためのもの。この記事では、合格のカギとなる判断基準を、面接官の視点から具体的に解説します。
1.学力よりも「読み解く力」が問われている
大学院の筆記試験、特に英語の問題を見ると「全文訳」「論文読解」が中心で、TOEICや英検のような文法問題はほとんど出題されません。
これはつまり、「英語力」というよりも、先行研究を読んで理解できるかを見ているのです。
なぜなら、大学院では日々、英語文献を読み、引用し、批判的に考える力が必要とされます。多少英語が苦手でも辞書を使えばどうにかなる。でも、読む力・理解する力がないと卒業はできない──面接官はそこをシビアにチェックしています。



だからこそ、辞書の持ち込み可の試験も多いのです。
2.「熱意」は最強の武器になる
面接で合格を勝ち取る最大の要素が、熱意です。
大学院では入学後、ゼロから知識を身につけることも可能です。だからこそ面接官は、「この人は本当にこのテーマに情熱を持っているのか?」を重要視します。
熱意はどこで伝わるか?
それが研究計画書です。
- 自分のテーマについて、具体的に語れるか?
- なぜこのテーマに興味を持ったのか?
- そのテーマの現状や先行研究をどれくらい理解しているか?
「熱く語れる=知識がある=熱意が本物」という三段論法で、面接官はあなたを評価します。
3.計画力がないと「卒業できる」と思ってもらえない
いくら熱意があっても、「なんとなく調べたい」レベルでは大学院では通用しません。
面接官が見るのは計画性と実現可能性。
研究計画書で特に見られるのは以下のポイントです。
- 研究スケジュールが現実的か?
- 調査方法が具体的に書かれているか?
- 「アンケートをとります」といった曖昧な記述になっていないか?
たとえば、「なぜアンケートが必要なのか」「どのような質問項目を設定するのか」といったところまできちんと設計できていれば、この人は卒業できるなという評価につながります。
まとめ:合格する人は「卒業後」を想像できている
大学院入試は、「今の学力」よりも「卒業までやりきれるかどうか」が重要です。
- 論文が読めるかどうか
- 研究に対する熱意があるか
- 実行可能な計画が立てられるか
この3つがそろっていれば、合格はグッと近づきます。
研究計画書の添削、面接対策などお気軽にご相談ください
もし、「このテーマで熱意が伝えられているか不安」「調査方法が適切かどうか見てほしい」など、お困りのことがあれば、研究計画書の添削やアドバイスも承っています。
お気軽にお問い合わせください。あなたの大学院合格を全力でサポートします!
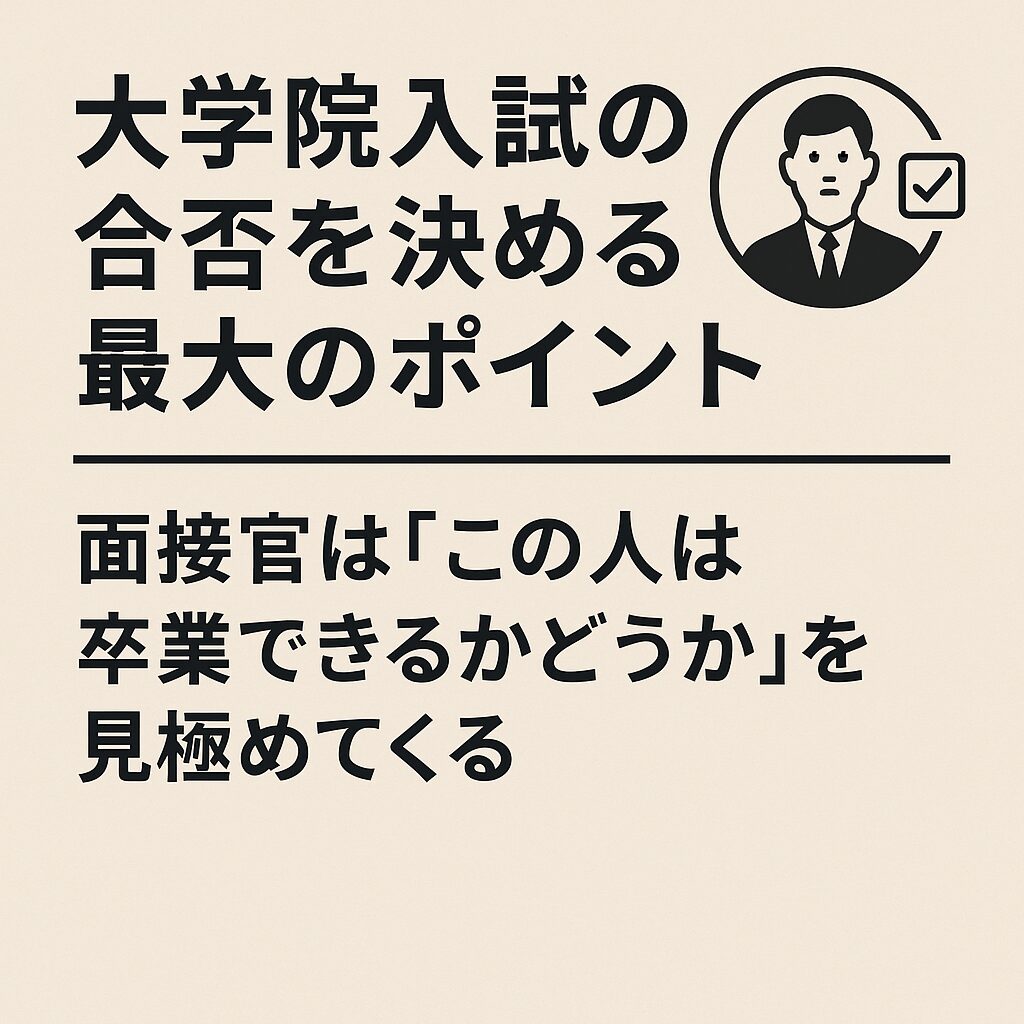
コメント