はじめに:模擬授業の「正解」、知らないままで大丈夫?
教員採用試験の中でも、多くの人がつまずくポイント――それが模擬授業や授業案の作成です。
「自分なりに工夫したのに評価されない…」「そもそも何を見られているのか分からない」
そんなモヤモヤ、感じたことはありませんか?
実は、評価には明確な基準があり、そこを押さえるだけで授業案の印象はガラリと変わります。

今回は、これまで数多くの模擬授業を見てきた現場の視点から、実例を交えて「評価される授業」のつくり方を解説します!
1.模擬授業は「アイデア勝負」じゃない
まずお伝えしたいのは、模擬授業で合否が分かれるのは「面白いアイデアがあるか」ではありません。
むしろ、評価者は“安定した授業ができるか”を見ています。
つまり、「この人なら子どもたちの前に立っても大丈夫だな」と思わせられるかどうか。
では、具体的にどこが見られているのか?ここからは評価ポイントを、ダメな例と改善案付きで解説していきます!
2.【評価ポイント①】基本的なルールを守れているか?
意外と多いのが、形式や提出ルールのミスです。
- 指定された用紙やフォーマットを守れていない
- 文字数や枚数がオーバーしている
- ファイル名が違っている
こういったミスは、それだけで「基本ができていない」と判断されてしまいます。
授業の中身以前の問題で評価が下がるのは、あまりにももったいない!
まずは“守るべきこと”をしっかり守る。ここが合格への第一歩です。
3.【評価ポイント②】「工夫」が“ただの言葉”になっていないか?
よく見かけるのが、
「振り返りを行います」
「意見を交流します」
といった表現。でも、「どうやって?」が書かれていないと、評価は伸びません。
❌ NG例:
「前回の学習を振り返る時間を設ける」
→ ただ書くだけでは、何も伝わりません。
✅ OK例:
「前回の学習内容を3つカードに書き出し、ペアで発表し合うことで記憶を定着させる」
→ これなら、「具体的に何をするのか」「どう効果があるのか」がハッキリ伝わりますよね。
4.【評価ポイント③】問いに“芯”があるか?
良い授業には必ず、*子どもたちの思考を引き出す“主発問”があります。
この問いがあることで、活動に意味が生まれ、子どもたちは考え、対話し、深めていくのです。
❌ NG例:
「漁業の課題を調べてスライドにまとめる」
→ 単なる作業に終わってしまいます。調べて終わり、になりがち。
✅ OK例:
「なぜ漁獲量は減っているのに、スーパーの魚は減らないのだろう?」
→ 興味を引く問いで、思考が広がります。さらに調べる意味も明確に!
授業案には、このような「考えたくなる問い」を軸に置きましょう。
5.【評価ポイント④】ICTやグループ活動に“意味”があるか?
「iPadを使う」「スライドにまとめる」などの活動は便利ですが、それ自体は評価されません。
大切なのは、「なぜその活動を入れたのか」です。
❌ NG例:
「iPadで資料を調べて、まとめます」
→ 調べて終わり?まとめるだけ?目的が見えません。
✅ OK例:
「3つの資料から必要な情報を取捨選択し、意見を組み立てる」
→ 情報活用能力の育成や、表現力の向上といった“ねらい”が伝わります!
6.評価者は「この授業、受けてみたい」と思うかどうか
評価する立場からすると、授業案を見て自然とこう思えるかどうかが一つの基準です。
- 子どもが主体的に動いているか
- 教師の指導が明確にイメージできるか
- 「学びのゴール」がはっきりしているか
評価される授業案には、自然とストーリーがあるんです。
まとめ:授業案づくりのチェックリスト(保存版)
最後に、模擬授業対策のためのチェックリストをまとめました。
✅ 提出形式・ルールを守っているか?
✅ 活動や発問の「目的」が書かれているか?
✅ 「思考の芯」になる主発問があるか?
✅ グループ活動やICT活用に意味があるか?
✅ 授業の流れがイメージできるか?
おわりに:授業づくりの“視点”が変われば、評価も変わる
模擬授業で大切なのは、斬新さや派手さではなく、「意図を持って考え抜いたかどうか」です。
そして、その意図が読み手(=評価者)に伝わること。
少し視点を変えるだけで、授業案は見違えます。
あなたの授業が「この子たちに届けたい!」と思える内容になるよう、ぜひ今回の具体例を参考にしてみてください。
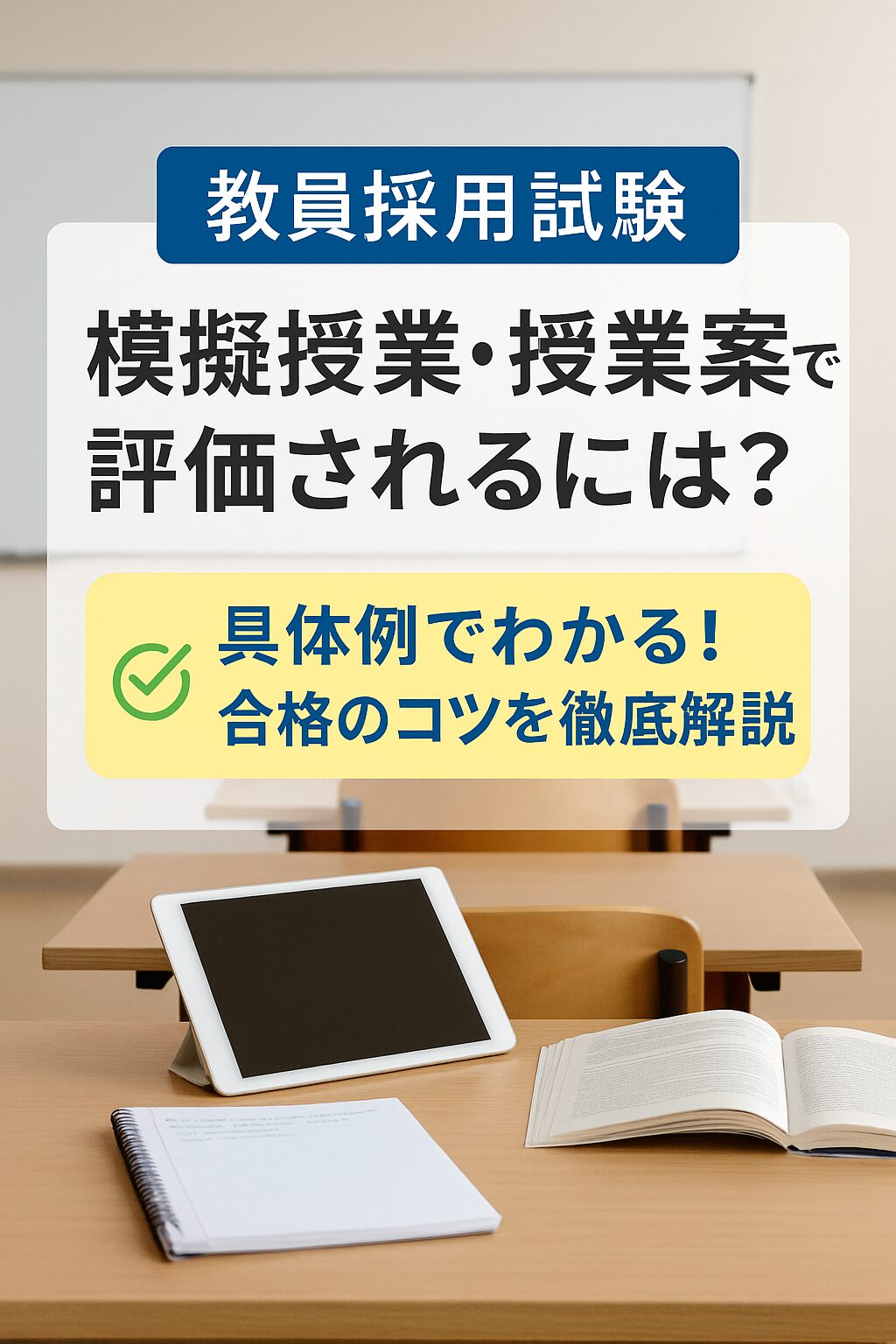
コメント